
高層ビルや住宅、商業施設が多く立ち並ぶ大都会東京。そんな中でも公園や街路樹などにはたくさんのセミが生息しています。今回はそんな大都会東京の都心部や周辺の関東平野でもよくみられるセミ5種類と、生息するけど少し珍しいセミ数種類についてまとめて解説していきます。東京のセミ事情に詳しくなろう!
東京都には何種類の蝉が生息するの?
単刀直入にいうと、東京都には合わせて14種類のセミが生息しています。日本全体には37種類のセミがいるので、その3分の1以上は東京都にいるという計算になりますね。
アブラゼミ アカエゾゼミ エゾゼミ エゾハルゼミ オガサワラゼミ クマゼミ コエゾゼミ チッチゼミ ツクツクボウシ ニイニイゼミ ハルゼミ ヒグラシ ヒメハルゼミ ミンミンゼミ
ただし、14種類すべてが都内に満遍なく分布しているわけではありません。セミは種類ごとに適した生息環境や場所があります。オガサワラゼミは種名の通り小笠原諸島にしか生息しませんし、エゾゼミやハルゼミなどの数種類は都内の街中で見かけることはまずありません。市街地にも分布する種類から山間部にのみ分布する種類、特定の樹種に依存する種類などさまざまです。以上のことを踏まえて14種類を整理します。
A:市街地や街中にも生息する種類
アブラゼミ クマゼミ ツクツクボウシ ニイニイゼミ ミンミンゼミ
B:平地にも分布するがその生息地が環境によって限られる種類
チッチゼミ ハルゼミ ヒグラシ ヒメハルゼミ
C:山間部にのみ生息する種類
アカエゾゼミ エゾゼミ エゾハルゼミ コエゾゼミ
D:島嶼部にのみ生息する種類
オガサワラゼミ
A~Dに分類しました。黄色線は23区内にいる種類です。注意点として、Cは山間部に「のみ」生息する種類を指します。Cに含まれないアブラゼミやヒグラシなど多くの種類は山間部にも分布します。オガサワラゼミは東京都の小笠原諸島にしか分布しないため、東京のセミは13種類(島嶼部を除く)と表現されることも多いです。
この記事では、主に街中や公園などに幅広く生息し東京23区内でも見かける頻度の高いAのセミ5種類について主に触れていきます。また+αとして23区内に分布するヒグラシや、その他のB~Cのセミについても軽く解説します!Dのオガサワラゼミについては省略します。
範囲を東京都から少し広げて関東地方にするとさらに2種類のセミが生息しています。
タケオオツクツク:埼玉県と神奈川県の一部地域の竹林
クロイワツクツク:千葉県南房総市の一部
いずれも元々は関東地方に生息しなかった外来種で、タケオオツクツクは中国大陸、クロイワツクツクは鹿児島県佐多岬〜沖縄本島にかけてが原産のセミです。


都内で身近なセミ5種類解説
東京都内や関東地方平野部の街中でよく見かけるセミ5種類について解説します!場所によっては以下の5種に含まれない、別のセミが街中でも見つかりことがありますが、基本的にはこの5種類が広く分布します。
アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata

全長:53〜58mm
分布:北海道〜屋久島
時期:7月中旬〜9月下旬
鳴き声:「ジージリジリ…」
鳴く時間:一日中(午後〜夕方が特に活発)
生息環境:市街地〜山地、公園、街路樹など
都内でのレア度:★☆☆☆☆(超普通種)
東京都内や関東地方では最も普遍的で広く見られる種類で、日本全国でも幅広く見られます。街中の街路樹や公園などでも数多く見られ、都市環境にかなり適応したセミのため見かける頻度も高いです。黒色の体に茶色く不透明な羽が特徴の大型のセミで、油で物を揚げる音のような鳴き声で鳴きます。都内では島嶼部の一部を除きほぼ全域で見られ、23区内にも多いです。アブラゼミについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


ミンミンゼミ Hyalessa maculaticollis

全長:55〜63mm
分布:北海道〜九州
時期:7月中旬〜9月下旬
鳴き声:「ミーンミンミンミンミー」
鳴く時間:一日中(主に午前中)
生息環境:東日本では市街地〜山地、公園
都内でのレア度:★☆☆☆☆(超普通種)
東日本では主に平地や市街地〜山地にかけて、西日本では山地のみで見られる大型のセミです。黒色の体にさまざまな緑色紋が入り、美しい見た目をしています。鳴き声が有名でアニメや映画の効果音として起用されることも多く、一度声を聞いたことがある人も多いはずです。東京都や関東地方では街中でもよく見られ、アブラゼミと並んで夏のセミとして親しまれています。23区内にもかなり多いですが場所によってその密度は異なり、個体数が少ない場所ではやや警戒心が高いです。ミンミンゼミについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


クマゼミ Cryptotympana facialis

全長:61〜68mm
分布:関東〜沖縄・八重山諸島
時期:7月上旬〜9月
鳴き声:「シャアシャア…」「ワシワシ…」
鳴く時間:午前中(天候不良の場合は午後)
生息環境:市街地、公園、街路樹など
都内でのレア度:★★☆☆☆(普通種)
主に西日本の温暖な地域に生息する大型のセミで、東京都内では最大の種類です。元々は神奈川県の西部が生息地の東限とされていましたが、植林の際の人為的移入など諸々の要因で東京都内にも分布を広げました。都内では沿岸部や23区東部、代々木公園などで多く見られ、そのほかの地域でも徐々に姿を見かけるようになってきました。ただ、場所によってはまだクマゼミは珍しく、ほとんど見られない場所もあります。アブラゼミと同様にかなり市街地に適応したセミで都市部の街路樹や公園に多く、大阪市内などでは大量に発生しています。午前中を中心に大声で鳴きますが、午後に鳴かないわけではありません。クマゼミについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


ニイニイゼミ Planopleura kaempferi

全長:33〜38mm
分布:北海道〜沖縄本島
時期:6月下旬〜9月
鳴き声:「ニーーーチーーー」
鳴く時間:ほぼ一日中
生息環境:市街地〜山地、公園、街路樹など
都内でのレア度:★★☆☆☆(普通種)
ほぼ日本全国に幅広く分布する小型種で、前翅のまだら模様が特徴的です。頭部から腹部にかけての紋様は緑色からオレンジ色とさまざまで個体差があります。アブラゼミやミンミンゼミなど他のセミと比べて早くから出現し、例年6月下旬ごろには初鳴きが観測されます。鳴き声は他のセミほど目立ちませんが、時間帯や天候にさほど左右されずほぼ一日中鳴きます。都内や関東地方では1970年代以降に数を減らしていましたが近年は増加傾向にあり街中でも姿を見つけやすくなりました。それでもアブラゼミほどに都市環境に適応したセミとは言えず、都心部での遭遇頻度はアブラゼミよりは低い印象です。(小型で目立たないことも要因ですが…)都内や関東地方のほぼ全域で広く見られ、乾燥していない柔らかい土壌がある場所を中心に多いです。ニイニイゼミについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


ツクツクボウシ Meimuna opalifera

全長:40〜47mm
分布:北海道〜屋久島・トカラ列島
時期:7月中旬〜10月
鳴き声:「オーシンツクツク」かなり複雑
鳴く時間:一日中(午後〜夕方が特に活発)
生息環境:市街地〜山地、公園、雑木林など
都内でのレア度:★★☆☆☆(普通種)
起承転結のある複雑な鳴き声が特徴の小型〜中型のセミです。ツクツクボウシほど複雑な鳴き声のセミは世界的に見てもかなり珍しいです。沖縄や奄美地方を除く日本全国に広く見られ、一日中鳴きますが午後や夕方が最も活発です。他のセミよりも出現がやや遅く、最盛期も8月下旬とやや遅いです。その分10月にいなっても鳴き声が聞こえることがあり秋のセミのイメージが浸透しています。都内や関東地方ではほぼ全域で見られ街中にも生息しますが、どちらかというと森林性のセミなため市街地ではアブラゼミほど多くありません。公園や神社などのまとまった木々のある場所付近や民家の庭などでよく見られます。ツクツクボウシについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


都内では少し珍しいセミ
東京都や関東地方には前述の5種以外にも数種類セミが生息します。その中でも23区内にも局地的に生息するヒグラシや、その他見つかる可能性のある種類を紹介します!
ヒグラシ Tanna japonensis

全長:42〜50mm
分布:北海道〜九州・奄美大島
時期:6月末〜9月上旬
鳴き声:「カナカナカナカナ…」
鳴く時間:早朝と夕方
生息環境:大きめの公園、雑木林、山地
都内でのレア度:★★★☆☆(局所的)
「カナカナカナカナ…」と哀愁漂う美声で早朝と夕方の薄暗い時間帯に鳴きます。北海道南部から九州まで幅広く生息しますが、日本固有のセミで海外には分布しません。平地から山地にかけて見られますが、森林性のセミで、生息地はある程度の樹木がまとまった環境に限られます。関東地方では郊外の大きめな林に行けば簡単に出会えますが、23区内では生息地がかなり限られます。明治神宮や小石川植物園などで確認されていうようです。晩夏のセミというイメージがあるようですが実際はその逆で、アブラゼミなどの夏のセミよりもやや早く出現し、7月下旬〜8月上旬に最盛期を迎えます。ヒグラシについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!


その他見つかる可能性のあるセミ
平地にも分布するがその生息地が環境によって限られる種類

全長:31〜37mm
分布:福島県・新潟県〜九州
時期:4月下旬〜6月末
鳴き声:「ムゼームゼー」「ンギィー…ンギィー…」
鳴く時間:よく晴れた午前中〜昼過ぎ
生息環境:平地〜山地の松林
都内でのレア度:★★★★★
(局所的で珍しい)
都内や関東、本州・九州(南西諸島を除く)で最も早く出現する春のセミで、平地ではゴールデンウィークの頃に最盛期を迎えます。かなり偏食のセミでアカマツやクロマツなどの松林とその周辺にしか生息しません。関東や都内では近年の松枯れによる松林の減少とその対策薬剤の散布により数を減らしていて、昔は23区内でも見られたものの現在ではすでに絶滅したとされています。東京多摩地域や関東地方ではゴルフ場などの松林の周辺に局地的に見られます。ハルゼミについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!

全長:33〜38mm
分布:茨城県・新潟県〜奄美諸島
時期:6月下旬〜8月上旬
鳴き声:「ヴィーン…ヴィーン…」
鳴く時間:夕方の日没前後
生息環境:シイ・カシ類の常緑広葉樹林
都内でのレア度:★★★★★
(局所的で珍しい)
ニイニイゼミとほぼ同時期に出現し、合唱性が高く、夕方の日没前後を中心に複数個体が大合唱します。ハルゼミと同様に生息環境は限られ、シイやカシ類からなる常緑広葉樹林にのみ見られますが局所的です。神社や寺院の社寺林のような昔から開発されていない環境見られることが多く、関東の生息地もそのような事例がほとんどです。茨城県、千葉県、新潟県の生息地では国の天然記念物に指定されています。都内では23区内では見られず西部の多摩地域でわずかに見られる程度です。

全長:27〜33mm
分布:北海道函館〜九州
時期:7月中旬〜10月下旬
鳴き声:「チッチッチッチッ…」
鳴く時間:日中
生息環境:※マツやスギなどの針葉樹林
都内でのレア度:★★★★★★★
(局所的でかなり珍しい)
東日本の山地では7月に見られることがありますが平地や西日本では出現が遅く、9月に最盛期を迎えます。(※)マツやスギなどの針葉樹を好みますが、広葉樹でも見られることがあります。しかし、ツツジ類の植物に産卵するため林床にツツジ類の植物が見られる場所とその周辺にのみしか生息しません。南関東ではかなり貴重なセミで都内だと多摩地域のごく一部でしか見られません。
山間部にのみ生息する種類

全長:37〜45mm
分布:北海道〜九州
時期:5月中旬〜7月末
鳴き声:「ミョーキン…ミョーキン…ミョーケケケケケ…」
鳴く時間:朝〜夕方
生息環境:標高700〜800m以上の山地
都内でのレア度:★★★★☆(山地性)
関東地方より西の地域では標高700〜800m以上の山地に、北海道や東北では平地〜山地にかけて生息する寒冷地を好むセミです。様々な樹木を好むため、関東でも標高が高ければ普遍的に見られることが多く、都内でも奥多摩などで見ることができます。出現が早く6月に最盛期を迎えます。

全長:59〜68mm
分布:北海道〜九州
時期:7月中旬〜9月
鳴き声:「ギーーーーーー」
鳴く時間:日中(午前中中心)
生息環境:標高500〜1000mの山地
都内でのレア度:★★★★☆(山地性)
北海道や東北では平地〜山地に、関東より西の地域では標高500〜1000mの山地に棲む寒冷地を好むセミです。マツやスギなどの針葉樹林に多いですが広葉樹でも見られます。頭を下にして木の枝先に止まることが多く見つけるのは難しいです。関東では山地に広く分布し都内でも奥多摩や高尾山周辺に広く見られます。

全長:50〜56mm
分布:北海道〜広島県・四国
時期:7月上旬〜9月上旬
鳴き声:「ビーーーーン」
鳴く時間:日中(午前中中心)
生息環境:標高900〜1500mの山地
都内でのレア度:★★★★★
(山地性でかなり標高が高い場所限定)
エゾゼミより一回り小型のセミで北海道や東北では平地〜山地で、関東より西では標高900〜1500mの高山で見られます。エゾゼミよりもさらに寒冷地を好むセミで様々な樹木を好みます。関東でも高山で多く見られ、都内でも奥多摩のかなり標高の高い場所に生息しています。

全長:60〜68mm
分布:北海道〜九州
時期:7月中旬〜9月
鳴き声:「ビーーーーン」
鳴く時間:日中(午前中中心)
生息環境:標高600〜1200mの山地
都内でのレア度:★★★★★★★
(山地性でかなり珍しい)
エゾゼミととても似ていますが、前翅の暗色紋の数や中胸背の白粉の有無で見分けられます。関東より西の地域では標高600〜1200mの広葉樹林(特にブナ林)に見られますがエゾゼミほど多くなく、生息地も局地的で珍しいです。関東でも生息地は局地的で都内にも生息しますが非常に珍しセミです。
まとめ
・東京都には14種類のセミが生息する
・東京23区内には6種類のセミが生息する
・アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミ、ニイニイゼミ、ツクツクボウシが街中でよく見られる
・生息環境や標高が限られる種類も存在する
東京に棲むセミの種類は多いと感じますか?それとも少ない…?
数種類のセミについてはさらに詳しく解説した記事があるのでそちらもあわせてご覧ください〜
参考文献
・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011
・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019
・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990
・沼田英治 初宿成彦『都会にすむセミたち』海游館 2007
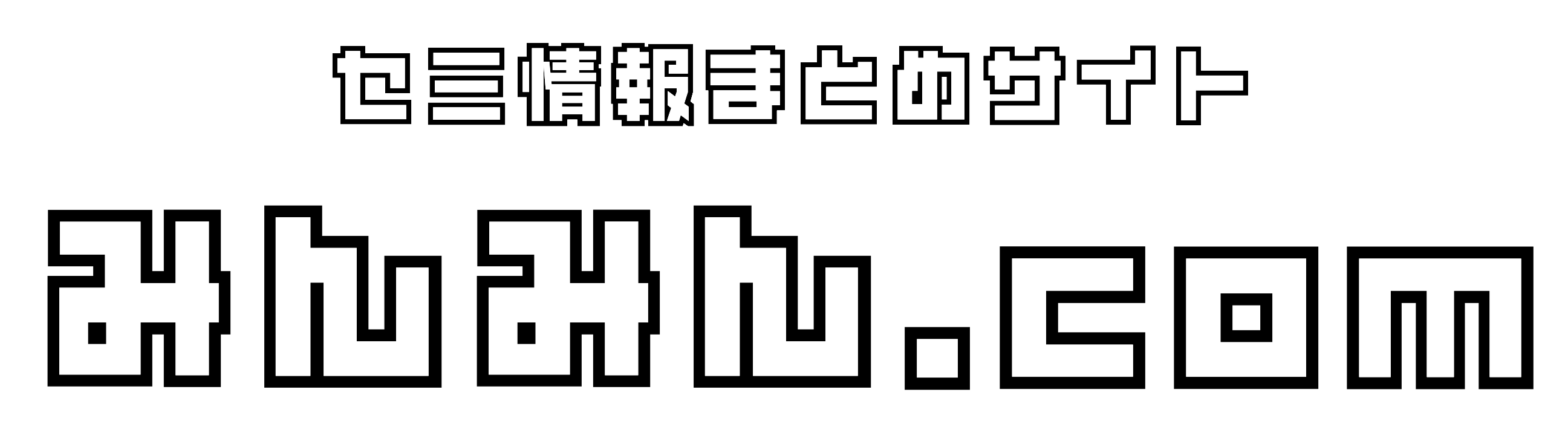














コメント