
「セミの寿命は1週間」なんて話よく耳にしますよね?その命の短さから儚さの象徴として扱われることが多々あります。しかし!これは嘘です!セミの寿命は1週間ではありません。意外と知られていないセミの基本的な生態についての総まとめです。簡単にわかりやすく解説します!これを知れば明日から誰かに自慢できるかも!?
そもそもセミってどんな生き物?
セミは一体どんな生き物なのでしょうか。以下は学術的なセミの分類です。
動物界>節足動物門>昆虫網>カメムシ目(半翅目)>頸吻亜目>セミ型下目>セミ上科>セミ
セミは昆虫の仲間で、頭・胸・腹の3節から構成され、3対6本の脚と2対4枚の翅を持ちます。昆虫の成長過程には卵→幼虫→蛹を経て成虫になる完全変態(カブトムシやクワガタなどの甲虫類、チョウやガなど)と卵→幼虫→成虫と蛹にならず成虫になる不完全変態(バッタやトンボなど)がありますが、セミは後者の不完全変態で蛹にはならず、幼虫状態から直接羽化して成虫になります。口の形がカメムシと同様にストロー状になっているためカメムシ目に分類され、意外ですがセミはカメムシやアメンボと近縁です。セミはストロー状の口(口吻といいます)を木に刺して、樹液を吸って生きています。
セミはとても面白い昆虫で、ほとんど全ての種のオスの腹部には発音器官が備わっていて大きな音で鳴き、腹部にはオスメスともに聴覚器官を持ちます。これはほとんどセミ特有のもので、鳴き声を発してオスはメスに求愛し、子孫を残しています。そのためメスのセミは鳴きません。鳴くのはオスだけです。
専門用語もあってややこしかったかもしれませんが、簡単にまとめると、
セミはカメムシの仲間の昆虫で、蛹(さなぎ)にはならず、食べ物は木の樹液で、オスが一生懸命鳴いてメスにプロポーズしている、ということです。




セミの一生
寿命は一週間ではない!
有名な話で「セミの命は1週間」というものがあります。その影響からなのか、儚さの象徴としてセミが描かれることもしばしば。確かにヒグラシの声なんかは儚いような寂しいような雰囲気があるので納得ではあります。でも、セミの寿命は1週間ではありません。もし外敵や天候などの外的要因により死亡しなければセミは3週間〜1ヶ月ほど生きると言われています。まだまだ研究途中で完全に解明されたわけではありませんが、飼育下で1ヶ月以上生きた事例や、野外でのマーキング調査で3週間前に捕獲されたクマゼミが再採集された事例などがその根拠となります。しかし、多くのセミは3週間や1ヶ月生きることなく外敵に捕食されるか、悪天候、羽化不全を理由に死んでしまいます。そう考えると、セミの平均寿命は1週間程度、あるいはそれ以下だと考えられるため、「セミの命は1週間」という話はあながち間違っていないのかなと思います。ただし今までの話は全てセミの成虫の寿命の話です。幼虫期間を含めたらどうでしょうか?


卵・幼虫
実はセミは幼虫期間を含めると、昆虫の中でかなり長生きです。寿命の話の前にセミの幼虫の基本的な生態について触れておきます。セミの卵はメスによって木の樹皮や枯れ枝、木の柵、生枝などさまざまなところに産み付けられます。産卵する場所は種類によって異なります。その後、産み付けられた卵は雨が振ることの多い秋雨の時期(9月ごろ)、または梅雨の時期(6月ごろ)に孵化します。孵化した直後の幼虫はとても乾燥に弱いためこうした湿った時期に孵化します。孵化の時期はセミの種類によって決まっていて、ニイニイゼミやハルゼミ、ヒグラシなどは秋に孵化する一方、アブラゼミやミンミンゼミ、ツクツクボウシなどは梅雨に孵化します。孵化したら幼虫はそのまま地面に落下して湿った地面に潜り、その後成熟して羽化する時まで基本的にはずっと地中で過ごします。地中では木の根付近に小さな部屋を作り、そこに定着して木の根の樹液を吸って成長します。成長に伴い部屋を拡張したり、場所を移動したりすることもあります。4回の脱皮を行い5齢幼虫になり、完全に成熟したら羽化のために地表付近で待機し、地上の様子を伺いつつ良いタイミングで地上に現れ羽化をします。それでは寿命の話に戻りましょう。これまた有名な話に「セミは7年間幼虫で過ごす」というものがあります。こちらも間違いです。セミの幼虫についてはほとんどずっと地中で過ごすことからあまりその生態が解明されていないのですが、どの種もきまって幼虫期間が7年、というわけではないことが飼育実験により確認されています。現段階では飼育したで大型のクマゼミやアブラゼミ、ミンミンゼミは2〜5年、小型のニイニイゼミが3〜4年、ツクツクボウシが1〜2年の幼虫期間であることがわかっています。幼虫期間は同じ種類でもその長さが異なり、これは各個体が吸収する樹液の質や量が異なるためと考えられています。また、野生下の幼虫は飼育下の個体に比べ、天候や吸収する樹液の栄養状態などの影響を受けやすいためより幼虫期間が長くなる傾向にあると予想されています。ちなみに幼虫期間が最も長いとされているのはアメリカの周期ゼミの一種のジュウシチネンゼミで、名前の通り幼虫期間は17年です。地上に現れて成虫になれば、そのセミは17歳です。ちょっと考えられない長さですよね…


羽化
無事に幼虫期間を全うした個体はいよいよ羽化をします。羽化とは読んで字の如くですが羽を手に入れること、つまり昆虫が羽のない幼虫または蛹から脱皮して成虫になることです。羽化は必ずしも成功するわけではありません。羽化途中に力尽きて死亡してしまうことや、羽化中は簡単に動くことができず非常に無防備になるためすぐに外敵に襲われやすくなります。そのため、セミにとって羽化は超重要イベントです。羽化は一部の種類を除き基本的に夕方から夜間にかけて行われます。昼間は外敵が多いためこのような暗い時間に羽化します。地中から現れた幼虫は羽化に最適な足場を探し歩き回ります。羽化は木の枝や幹、葉、人工物など様々な場所で行われ、天候や湿度により変動があるものの、1時間程度で終了します。羽化直後の体は柔らかく白っぽい色をして大変美しいですが、時間経過とともに体が固まり、翌朝には普段見慣れた色になります。
羽化について詳しくはこちらの記事でまとめていますのでぜひご覧ください〜



鳴き声
羽化を終えたオスのセミはすぐには鳴けません。羽化から数日間は体が未成熟で発音器官も成熟していないためです。オスのセミは腹部の腹弁の下にある発音筋で発音膜を動かして音を出し、共鳴室でその音を増幅させています。詳しいセミの鳴く仕組みについては別の記事で紹介していますのでそちらをご覧ください。
鳴き声はセミの種類によって異なります。鳴き声にはいくつかの種類があり、メスに求愛するための主鳴音(本鳴き)、メスが接近した時に調子を変えて鳴く交尾誘導音など繁殖に関わることがメインですが、休息中や夜間に「ギッ!」と突然呟くように鳴く休息音、外敵に襲われた時に出す悲鳴音などさまざまです。他にも数種類の鳴き声のパターンがあります。一部種類では同じ場所で1回か複数回鳴いたのちに別の場所へ飛び移って再び鳴くことを繰り返す鳴き移りを行います。これはミンミンゼミやヒグラシなどでよく見られます。また、どのセミも1日のうちで活発に活動して鳴く時間帯がおおよそ決まっています。例外もありますがアブラゼミなら午後から夕方にかけて、ヒグラシは早朝と夕方の薄暗い時間、クマゼミは午前中によく鳴きます。ただしこれ以外の時間帯に鳴くこともあります。


セミは何を食べる?
すでに何度か触れていますが、セミが食べるものは樹液だけです。食べるというより飲むの方が適切かもしれませんね。腹面にある口吻(こうふん)と呼ばれるストロー状の口を木の樹皮に突き刺して樹液を吸います。吸汁した樹液から必要な栄養素を吸収したら、残りの水分は尿のようにして排出します。「セミにおしっこをかけられた」なんて苦い思い出があるかもしれませんが、その正体はただの水ですのでたいして汚くはありません。セミは外敵から逃げるなどの理由で飛び立つ時に少しでも体を軽くするために排泄をすることが多いです。だから、近づいてきた人間に驚いたセミのおしっこが人間にかけられがちなんです。そして実は、セミには樹液の好き嫌いがある種類がいます。ハルゼミはかなりの偏食で松の木の樹液しか好みません。また、クマゼミはいろんな木の樹液を吸いますが特にセンダンの木が好きなようで、周囲にたくさん木があっても分散せずセンダンの木に群がることがあります。上記2種ほど顕著ではないものの、他にもアブラゼミやニイニイゼミはサクラやケヤキを好み、エゾゼミが松や杉などの針葉樹を好む傾向にあります。


交尾・産卵
鳴き声がメスに認められてらメスは鳴くオスに接近します。メスが接近したら、一部の種類のオスは鳴き声の調子を変えてメスにアピールします。これが交尾誘導音と呼ばれる鳴き声です。そのあとメスに気に入られたら交尾をします。交尾はオスとメスの腹部末端にある生殖器を接合させて基本的にはV字型で行われますが、一部種類はオスとメスが反対を向いた反向型で交尾します。約10〜30分程度交尾状態が維持されます。しかしながら、メスが接近してきたからといって必ずしも交尾が成立するわけではありません。不遇にも交尾を拒否されてしまうことが多々あります。
交尾を終えたメスは産卵します。卵・幼虫の部分で触れましたが、メスは腹部末端にある産卵管を木の樹皮や枯れ枝などに刺しこんで産卵します。多くのセミは樹皮を含め植物の枯れた部分に産卵しますがイワサキクサゼミやチッチゼミなど一部では生きた植物に産卵することがあります。また、セミには吸汁する樹液に好き嫌いがありますが産卵する木の種類には無関心なようで、大きさや形が合えば何にでも産卵します。木の柵やネット、電線などの人工物に産卵した事例もあります。1匹のメスからは300〜800個ほどの卵が産み付けられると言われています。産卵によって産卵された植物にはささくれや亀裂のような産卵痕ができ、その形はセミの種類によって違います。産卵管などのセミの体の構造について詳しくはこちらの記事をご覧ください。




最期 セミの天敵について
セミの死因はさまざまです。前述のように1匹のメスから300〜800個の卵が産まれますが、その中で無事に成虫になれるのは一部に過ぎません。厳しい生存競争です。幼虫期間では孵化不全や脱皮不全のほか、アリやモグラなどの外敵に襲われることや、冬虫夏草と呼ばれる昆虫寄生菌に感染することがあります。冬虫夏草はセミの幼虫やその他の昆虫を宿主として菌を繁殖させ、キノコのようにして地上に顔を出して胞子を撹拌させることで、新たな宿主に感染して繁栄します。オオセミタケやツクツクボウシタケなどセミの特化した種類も知られています。十分成熟した幼虫は羽化します。羽化やそのために地上に姿を表した幼虫は動きが鈍くまだ飛んで逃げることができないため外敵に襲われることが多いです。また、羽化に失敗してそのまま死んでしまう羽化不全も稀ではありません。


無事に成虫になってもセミには外敵の脅威から避けられません。セミは飛んで逃げる以外に防御手段を持ちません。そのためセミは食物連鎖においてかなり下方に位置します。セミの天敵として代表的な生物は以下の通りです。
・ニホンザルやクマ、人間などの哺乳類
・カラスやヒヨドリなどの鳥類
・トカゲやカエルなどの両生類爬虫類
・トンボやスズメバチ、カマキリ、キリギリスなど他の肉食昆虫
・ムカデやクモなどの節足動物
・セミに寄生するハエ
・昆虫寄生菌
非常に多種多様な外敵がいます。もちろん人間もセミにとっては驚異的な外敵です。物理的な捕食が多いですが、中には寄生バエや菌によるものもあります。寄生バエは幼虫状態でセミの腹部に寄生し、発音筋や卵巣を食べてしまいます。寄生されていてもセミは生き続けることができますが途中で発音できなくなります。また、寄生バエの幼虫はある程度成長したらセミの腹部から脱出し、その後寄生されていたセミは死に至ることが多いようです。他に有名なセミに寄生する生き物としてセミヤドリガという蛾の仲間が挙げられますが、セミヤドリガの場合は寄生されても不便なだけで直接的に死に至ることはほとんどないようです。また、昆虫寄生菌によって死亡することも多く、有名なものにボーベリア菌があります。ボーベリア菌は多くの種類にセミや昆虫に感染し、感染したセミは木の幹や枝に爪や口吻を強く突き立てた状態で死亡します。その後体内で菌が成熟したら、セミの体節から白い綿のようなものが出現し死亡したセミの体を膨張させます。他にもさまざまな寄生菌が知られています。
外敵に襲われる以外にもさまざまな要因でセミは死に至ります。想像しやすいのが天候によるもので、悪天候時は葉の裏などに隠れてやり過ごしますが、一部は激しい雨や風、低温あるいは高温に耐えきれず死んでしまうことがあります。他にも単に地面に落下して起き上がれずに死亡する場合があります。セミは背中側を下にして地面に落ちてしまった場合、体力が残っていたり、付近に捕まれるものがあったりする場合にはすぐに起き上がれます。しかし、体力が残っていなかったり、付近に捕まれるものがなかった場合にはそのまま起き上がれずに死亡してしまいます。裏返って死んでいるだろうと思ったセミが近づくと突然暴れ出すセミファイナルに遭遇することがあるかもしれません。こうしたセミファイナルに陥るセミの多くは裏返った状態から起き上がれずに苦労しています。ファイナル状態のセミを見つけたら、そっと近くの木に止まらせてあげましょう。


セミの分布
日本のセミ
日本には現在確認されているだけで37種類のセミが生息しています。正確には36種類1亜種で、沖縄県の大東諸島にのみ生息するダイトウヒメハルゼミがヒメハルゼミの亜種として数えられています。そのうち沖縄県や奄美諸島などの南西諸島を除く日本本土で見られる種類は19種類で、沖縄を中心とする島嶼部にその種類が多いことがわかります。沖縄周辺は本土とは異なり亜熱帯の気候に分類され、その気候に特化した固有の種類が生息しているためで、これはセミに限った話ではなく多くの生物において共通です。セミの種類によっては好みの木や環境に左右され生息地が局所的になることがあり、東京の都市部で普通に見られる種類はアブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミ、ニイニイゼミ、ツクツクボウシの5種類のみです。郊外地域を含め東京都全体で見ると14種類が生息しています。(小笠原諸島固有の1種、オガサワラゼミも含む)

また、日本のセミには2種類の外来種が知られています。スジアカクマゼミとタケオオツクツクです。スジアカクマゼミは2001年に石川県金沢市で確認された中国や朝鮮半島原産の大型のセミで姿はクマゼミに似ています。移入経路はわかっておらず、発見以来生息地を拡大させることはほとんどなく非常に局所的です。在来種への影響はほとんどないものとされています。タケオオツクツクは2016年に埼玉県川口市で確認された大型のセミでツクツクボウシをそのまま巨大化させたような見た目をしています。その名の通り竹林に棲む変わった生態で、日没直後に大合唱します。中国原産で、中国から輸入された竹ぼうきに本種の卵が混入していたことで日本に移入されました。現在では川口市以外の場所でも確認されていますが、在来種への影響はまだよくわかっていません。


日本人とセミの関わり
日本ではセミは非常に身近な昆虫です。アニメやドラマの効果音として夏を演出するために鳴き声が使われ、古くから季語として短歌や俳句などに登場し現代でも季節を感じる代表的な風物詩となっています。「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」という松尾芭蕉の『奥の細道』に記された俳句は非常に有名ですね。この句は芭蕉が山形県の山寺(立石寺)を参詣した際に読まれたもので、訪れた時期からこの蝉の声の正体はニイニイゼミだと推定されています。この他にもセミはさまざまな歌の歌詞に登場し、日本人の文化にとってその存在は欠かせないものです。これは日本でセミが街中の身近な場所に普遍的に生息し、特徴的な鳴き声を発するからです。姿は見なくてもその声は嫌でも耳に届きます。その存在の分かりやすさゆえにセミはここまで文化に根付いた存在になり得たのでしょう。
世界的に見たセミ
日本でセミはポピュラーで身近な昆虫ですが、実は海外では日本ほど身近ではありません。セミは熱帯と温帯地域を中心に世界各地に分布しますがその種数はアジアやオセアニアに多く、日本では37種類なのに対し、日本の九州ほどの大きさの台湾には50種類以上のセミが生息しています。オーストラリアでは200種を超えます。一方、イギリスには1種類のみ、地中海沿岸地域には数種類のみとヨーロッパではセミは珍しい存在です。アメリカでは街中に住むような身近なセミが少なく、日本のセミのように特徴的な鳴き方をするものはあまりいません。その影響からか、アメリカやヨーロッパなどの海外ではセミの存在感が薄くマイナーな昆虫で、日本のように人々との関わりはほとんどありません。そのためセミの鳴き声は鳴き声として認識されておらず、雑音として扱われているようです。日本語では「ミンミン」や「カナカナ」などセミの声に対応する擬音語がありますが、英語圏では雑音として、ただの音としてセミの鳴き声を判別していないため、セミの声に相当する擬音表現はありません。セミの鳴き声を聞き分ける能力は日本人にしかないと言われるほど、日本は特別セミと人間の関わりが強い地域なのです。
まとめ
・セミはカメムシ目の昆虫で蛹にならない
・セミは木の樹液を吸って栄養にして生きている
・セミの成虫の寿命は必ずしも1週間ではない
・セミの幼虫は長い期間地中で過ごすが、その具体的年数はまだ詳しくわかっていない
・セミの羽化は主に夕方から夜間にかけて行われる
・セミの鳴き声や産卵場所はさまざまである
・セミには外敵がたくさんいる
・日本には37種類のセミが生息し、日本人の文化に密接に関わっている
・海外ではセミは身近ではなく、セミの鳴き声は声ではなく雑音のように扱われている
以上セミの基本的生態の完全解説でした。かなり長くなってしまいましたね…
しかしまだこれは基本的な生態に過ぎません。この記事では触れられなかった面白い生態がまだまだあります。今回書ききれなかったことは他の記事に載せようと思いますのでぜひ読んでみてください!この記事を読んでみてわからないことやもっと知りたいことがありますたらぜひコメントまでお願いします〜
参考文献
・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011
・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019
・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990
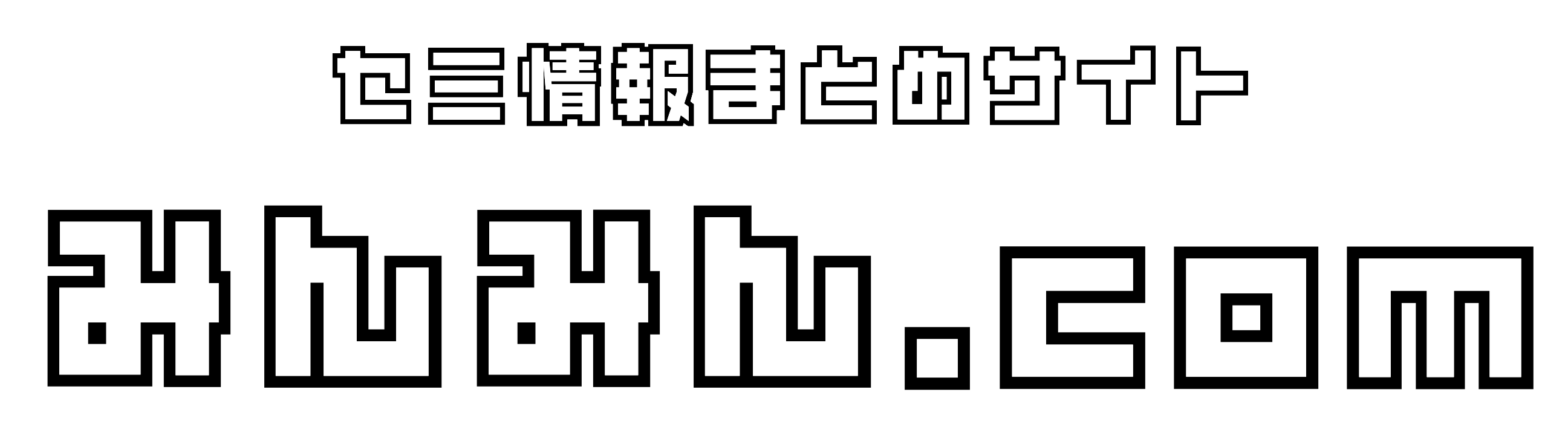









コメント