
そもそも春にセミなんかいるの?なんて思うかもしれません。それもそのはず。今回紹介する「ハルゼミ」は生息地が限られていて場所によってはとても珍しいセミなのです。そんなハルゼミについて、実際に撮影した写真を使ってその生態や特徴を徹底解説していきます!後半ではハルゼミを見つけるコツなんかも教えちゃいますよ〜
ハルゼミの基本情報


ハルゼミ
yezoterpnosia vacua
セミ亜科>ヒグラシ族>ハルゼミ属
見た目の特徴
オス:33〜37mm メス:31〜36mm (全長)
小型のセミです。オスの腹部は紙風船のようになっていて、内部で音を反響させて小さな体から大声を出します。メスの産卵管は長く突出するのが特徴。また、オスとメスとで大きさはそれほど変わりませんが、オスは全体的に黒っぽいのに対しメスは褐色の模様が入ります。ハルゼミのようにオスとメスで体の模様が異なる傾向にあるセミは珍しく、日本では他にタイワンヒグラシやクロイワツクツクなどの数種類に限られます。(※一部個体ではオスにもメスのように褐色の模様が入ることもあります)
セミ全種に共通する形態的特徴についてはこの記事をご覧ください!
分布
福島県・新潟県以南の本州、四国、九州、その他一部離島
北海道や東北地方の大部分、南西諸島には生息していません。また、後で詳しく解説しますがハルゼミは松林とその周辺にしかいません。そのため、上記の地域に満遍なく生息しているわけではなく、松林がある場所に限り点状に分布しています。関東では数が少なく生息地もかなり限られています。
時期
4月下旬〜6月末
ピークは場所によって違いますが平地では概ねゴールデンウィークの頃に、標高の高い山地では5月下旬に最盛期を迎えます。
南九州の一部地域では早くて3月末から発生することがあります。また、山間部では7月までみられることがあります。
鳴き声
一般的には「ムゼームゼー」と表現されることが多いですが実際に聞くと「カラカラカラカランギィィーーンギィィーー」といった感じで、よく晴れた日の午前中を中心に昼過ぎまで断続的に合唱します。他の個体の鳴き声に誘発されて次々と鳴き出す合唱性の強いセミで、全く鳴き声が聞こえない状態から一気に何個体も鳴き出すこともあります。時には車やバイクなどの騒音を他個体の鳴き声と勘違いして鳴き始めることも…。個体数が多い場合は頻繁に合唱しますが、逆に個体数が少ないと合唱とその後の合唱との間が数分や数十分ほど空く場合もあります。
生息環境
ハルゼミは日本のセミの中でも極端に偏食で、クロマツやアカマツなどの松林にしか生息しません。この偏食がハルゼミを身近に感じない要因の一つでしょう。松林内では松の幹ではなく横枝に好んでとまるため、木の高いところにいることが多くなかなか姿を見つけるのはかなり大変です。


羽化・抜け殻・産卵
羽化は他のセミ同様、主に夜間19時ごろから23時ごろに行われます。まれに日中にも羽化することがありますがこれは他のセミにもみられる事象のため、特筆すべき点ではありません。ハルゼミは出現時期が早い分、夜はまだ気温が低いことがあり、低温の場合は夏に羽化するセミと比べて羽化に時間を要することがあります。抜け殻は生息地の松の幹によくみられます。光沢があり非常に小さく薄めの色が特徴です。産卵は松の木の枯れ枝や樹皮に行われ、その年の秋に孵化します。セミの羽化についてこちらの記事で詳しくまとてていますのでぜひご覧ください!




ハルゼミを見つけるコツ
他のセミよりも一足早く出現するハルゼミ。珍しいセミなので一度はその鳴き声を生で聞き、その姿を見たいという方も少なくないはずです。ということでハルゼミを見つけるコツを教えちゃいます!
コツとはいっても大事なことはただ一つで、ハルゼミの生態を詳しく理解することのみです。前述の通り、ハルゼミは松林にしかいないのですから、当然松の生えていない場所を探しても見つかることはありません。まず鳴き声を聞くためにはハルゼミの分布域内の松林に向かいましょう。天候や時期も重要で、気温の低い日や雨の日は鳴きませんし、季節外れの2月や8月に松林に行っても声は聞けないでしょう。おすすめは平地や海沿いではよく晴れた5月上旬、山間部ではよく晴れた5月中旬〜下旬です。(その年の気候次第で前後する可能性もあります。)鳴き声が聞こえなくても抜け殻があればそこにハルゼミがいます。天気の良い日に改めて訪れてみると良いでしょう。また個体数の少ない場合、ハルゼミはいるのに全く鳴いていない、なんてときがあります。この場合、天候と季節の条件が良ければ数分〜数十分待つと一度は声が聞けるはずですが、ハルゼミの合唱性を利用して探す方法もあります。スマートフォンなどの端末からハルゼミの鳴き声を音量MAXで流してみてください。スマホからの音を他の個体の鳴き声だと勘違いしたハルゼミが誘発されて鳴き始めることがあります。嘘のような話ですがハルゼミは結構簡単にこの罠に引っ掛かります。ただし、分布域内の松林に行ってからといって必ずハルゼミがいるとは限りません。ここが難しいところで、松林の規模や立地など様々な要因で松はあるのにハルゼミはいない…なんてことはよくあります。筆者自身も何度もいろんな松林を訪れ、何度もハルゼミの生息しないハズレくじのような松林に行き着きました。もし行った先の松林にハルゼミの気配がなければ諦めて別の場所の松林に向かいましょう。

無事にハルゼミのいる松林にたどり着けたら、あとは姿を見たいですよね。しかしハルゼミは小型で色も地味なためなかなか探すのに苦労します。まずは鳴き声を頼りに根気よくオスの姿を探しましょう。ポイントとしては、松の幹よりかは横枝や枝先をよく探すことです。基本情報に書いてあり通りハルゼミは幹よりも枝を好みます。(もちろん幹にとまっていることもありますが…)これさえ理解すれば、オスの腹部が太陽光に透けてオレンジ色に見えるほか、ちょこちょこと枝先を歩き回りながら鳴くので意外と見つけられるようになります。(下画像4枚目のように)気温が高く良い天気の日にはよく飛びます。しかし、松の木の樹高が高いとその分枝も高い位置になるため見つける難易度が上がります。なるべく低い松の木のある場所を探しましょう。メスは鳴かないためオスを探すよりもかなり難しいですが、ちゃんとオスと同じような環境にいるのでオスを見つけられるようになったら似たような場所をじっくり探してみましょう。また、確実にハルゼミの姿を見たければ羽化の瞬間を狙うのも効果的です。羽化は人間の目線の高さで行われることも多く、羽化中はセミも逃げないためじっくりと観察することができます。





ハルゼミの現状
こうして紹介してきたハルゼミですが、現状その数を減らしています。原因は主に昨今の都市開発と全国的な松枯れによるものだと考えられています。松枯れとは、「マツノマダラカミキリ」というカミキリムシの仲間に寄生した「マツノザイセンチュウ」という小さな線虫に仲間が松の樹内に入ることで松を枯らしてしまう伝染病のことで、一度感染し枯れてしまうともう元には戻りません。こうした松枯れとその感染防止のために全国の松林が減少したことに加え、都市部では都市開発による松林の伐採が拍車をかけ、ハルゼミの減少につながっているのです。昔は東京23区内にもハルゼミが生息していたそうですが、現在23区内では絶滅してしまったと推定されています。また、23区部以外でも貴重な存在で絶滅危惧ⅠB類に指定されているほか、複数の府県で準絶滅危惧種として指定されています。こうした貴重な存在を守るためにも、同じ産地での乱獲や生息地の破壊行為は絶対にやめましょう。意味のない採集を控え、採集しても元いた生息地にリリースするのが良いでしょう。この際は必ずハルゼミを捕獲した場所で逃してください。それ以外の場所では絶対に逃がさないように。些細なことのように思えますがこの行動が生態系破壊へとつながる恐れがあります。また、採集して持ち帰り、標本にするなどの行為は全く悪いことではないと考えていますが、大量に乱獲するのは控えましょう。採集と乱獲は全く別です。どの昆虫を採集する時にも言えることですが、マナーを守って楽しみましょう。

まとめ
・ハルゼミは4月下旬〜6月末にかけてあらわれる、松林にしかいないセミ
・合唱性があり他の個体やその他の雑音に誘発させて鳴く
・松林があったとしてもそこにハルゼミがいないこともよくある
・ハルゼミは松の幹よりも横枝を好む
・ハルゼミは今、数を減らしている
ハルゼミについてよくわかっていただけたでしょうか?皆さんもぜひ一度は特別な春のセミ、ハルゼミを探してみてください!ハルゼミについて何か知っていることや疑問等ございましたら遠慮なく下のコメントまでどうぞ!お待ちしてます!
参考文献
・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011
・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019
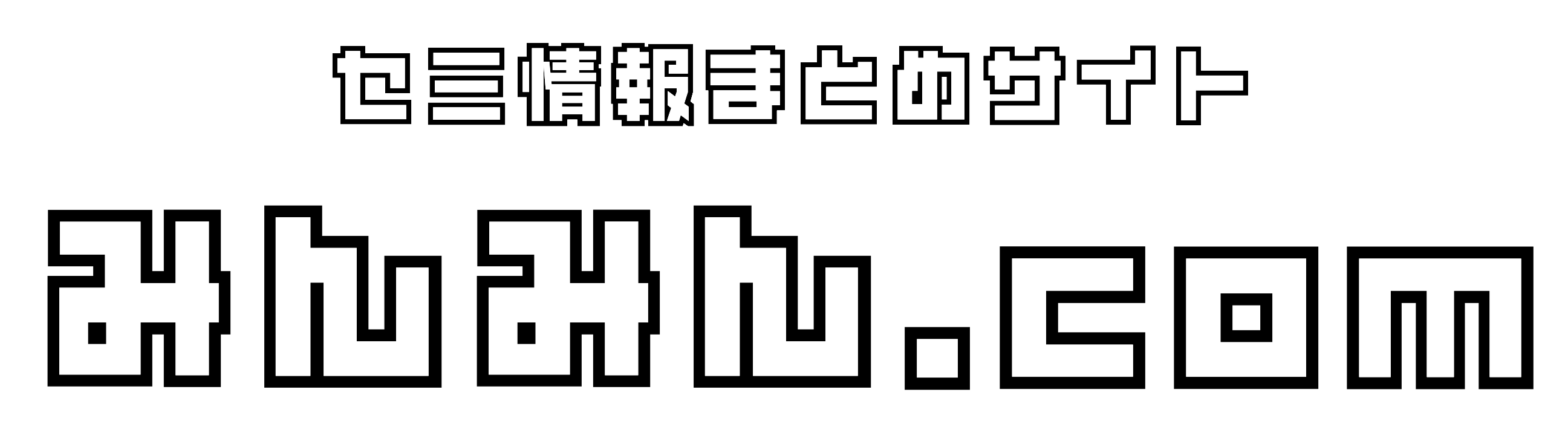









コメント